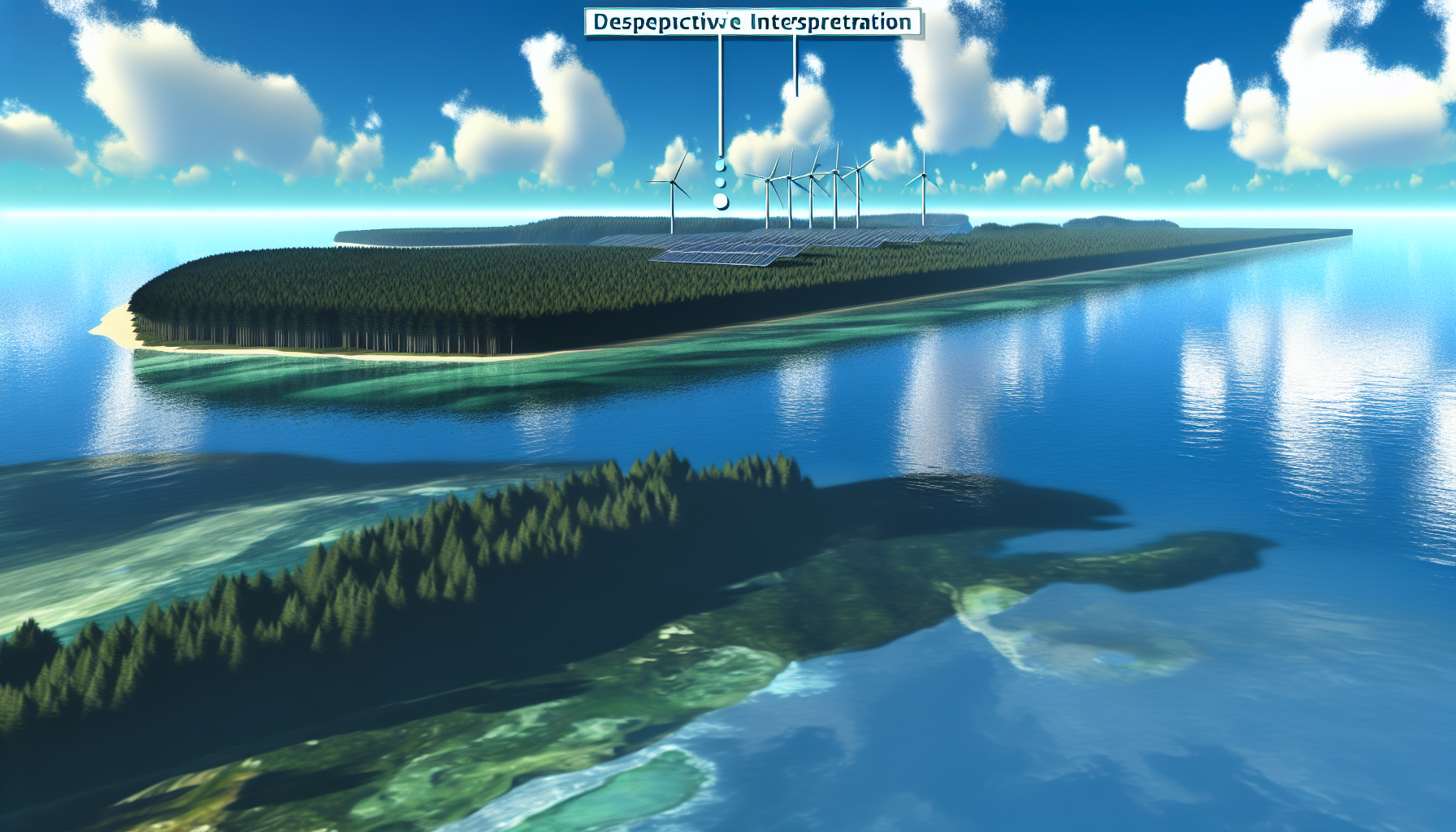目標13の概要
気候変動は、21世紀最大の脅威の一つです。産業革命以降、人間活動による温室効果ガスの排出により、地球の平均気温は約1.1℃上昇しました。この結果、異常気象の頻発、海面上昇、生態系の変化、食料生産への影響など、様々な問題が顕在化しています。
2015年に採択されたパリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすることが合意されました。しかし、現在の各国の削減目標を足し合わせても、今世紀末には約2.7℃上昇すると予測されており、大幅な削減努力の強化が必要です。
緩和と適応の両輪
気候変動対策には、「緩和」と「適応」の両方が必要です。緩和とは温室効果ガスの排出削減や吸収源の強化であり、再生可能エネルギーへの転換、省エネ、森林保全などが含まれます。一方、適応とは、すでに起こっている、あるいは避けられない気候変動の影響に対処することであり、防災インフラの強化、農作物の品種改良、水資源管理などがあります。
エネルギー転換
化石燃料から再生可能エネルギーへの転換。太陽光、風力、水力、地熱などの普及拡大が急務です。
産業脱炭素
製造業、運輸業での省エネルギー、電化、水素活用、CCUS技術の導入を推進します。
森林保全
森林減少の防止、植林、森林管理の改善により、CO2吸収源を強化します。
適応策
防災インフラ、早期警報システム、気候耐性作物の開発により、気候変動の影響に対処します。
気候変動の影響例
気温上昇: 熱波の頻発、農作物の品質低下、熱中症リスク増加
降水量変化: 洪水と干ばつの激化、水資源の不安定化
海面上昇: 沿岸地域の浸水、島嶼国の水没リスク
生態系変化: 生物種の絶滅加速、生態系サービスの劣化
カーボンニュートラルへの道
日本は、2050年カーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)を宣言し、2030年度に2013年度比46%削減という目標を掲げています。この実現には、エネルギー、産業、運輸、建築など、社会のあらゆる分野での脱炭素化が必要です。
分野別脱炭素化戦略
- 電力部門: 再生可能エネルギー比率を2030年36-38%へ拡大
- 産業部門: 省エネ、燃料転換、革新技術の導入
- 運輸部門: 電気自動車、水素自動車の普及拡大
- 家庭・業務部門: ZEH/ZEB、省エネ機器の普及
- 革新技術: 水素、CCUS、次世代太陽電池等
蓄電技術
再生可能エネルギーの変動性を補うため、大容量蓄電池やパワーツーガス技術を開発。
水素社会
クリーン水素の製造・利用拡大により、産業、運輸、発電分野の脱炭素化を推進。
CCUS技術
CO2回収・利用・貯留技術により、避けられない排出をオフセット。
国際協力
技術移転、資金支援、能力構築により、世界全体の脱炭素化に貢献。
気候資金とグリーンファイナンス
気候変動対策には膨大な投資が必要です。先進国は途上国への年間1,000億ドルの気候資金提供を約束していますが、実際の需要はその数倍に上ります。民間資金の動員が不可欠であり、グリーンファイナンス市場の拡大が期待されています。
グリーンファイナンスの拡大
金融セクターの役割
- グリーンボンドの発行拡大
- ESG投資の主流化
- 気候リスク開示の義務化
- 化石燃料事業からのダイベストメント
- トランジション・ファイナンスの推進
気候正義と公正な移行
気候変動は、貧困国や脆弱な立場の人々に最も深刻な影響を与えます。温室効果ガスをほとんど排出してこなかった国々が、干ばつや洪水、海面上昇により最大の被害を受けるという「気候不正義」の問題があります。先進国は、途上国への資金支援(年間1,000億ドル)と技術移転を通じて、この不均衡に対処する責任があります。
脆弱な人々への影響
小島嶼開発途上国: 海面上昇により存続の危機
アフリカ・サヘル地域: 干ばつと砂漠化の深刻化
沿岸地域住民: 高潮・台風被害の頻発
農業従事者: 収穫量減少と生計への打撃
公正な移行(Just Transition)
脱炭素化の過程で、化石燃料産業で働く労働者や、炭素集約的産業に依存する地域社会に配慮した移行が重要です:
- 労働者の再教育・スキルアップ支援
- 新たな雇用創出(グリーンジョブ)
- 影響を受ける地域への投資
- 社会保障制度の整備
日本の取り組み
日本は2050年カーボンニュートラルを宣言し、グリーン成長戦略を策定しています。また、国際的にはアジア・ゼロエミッション共同体構想を提唱し、アジア地域の脱炭素化を支援しています。
国内施策
地球温暖化対策計画
2030年度46%削減目標の達成に向けた部門別・分野別の対策を策定。
GX経済移行債
20兆円規模の投資により、クリーンエネルギー戦略の実現を支援。
カーボンプライシング
炭素国境調整措置の検討、排出量取引制度の拡充を推進。
イノベーション推進
ムーンショット型研究開発、グリーンイノベーション基金の活用。
国際協力
- アジア・ゼロエミッション共同体の推進
- 途上国への気候資金支援(年間130億ドル)
- 二国間クレジット制度(JCM)の展開
- 技術移転・能力構築支援
- 気候変動適応技術の普及